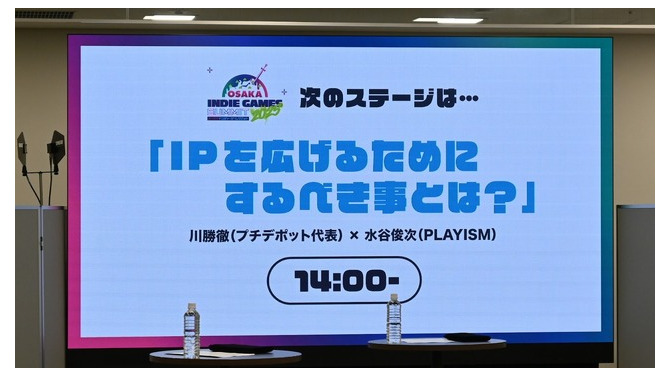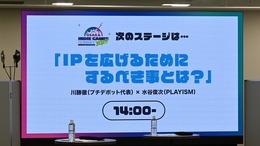10月4日と5日、大阪・梅田のグラングリーン大阪「コングレスクエア」にてインディーゲーム展示会「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT2025(OIGS2025)」が開催されました。
100を超えるタイトルが集まった会場では、ステージエリアにてトークイベントも実施。本稿では、ビジネスデーとなった10月4日に開催された、トークセッション「IPを広げるためにするべきこととは?」の模様を、対談形式でお届けします。
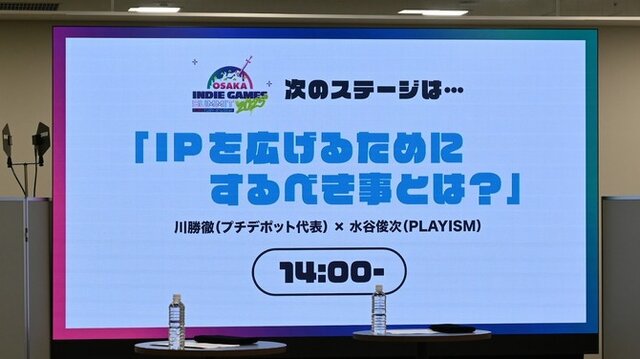
◆ゲーム実況の浸透で求められるビジネスの変化とIPの展開
トークセッションには、間もなくTVアニメも放映開始となる『グノーシア』開発のプチデポット代表・川勝徹氏。そして、『グノーシア』や映画化もされた『8番出口』のパブリッシングも手がける「PLAYISM」運営のアクティブゲーミングメディアより、水谷俊次氏が登壇。
ラジオ局FM802のDJを担当するハタノユウスケ氏による進行のもと、ゲームIPの広げ方をテーマにしたトークが繰り広げられました。

ハタノ氏:本日はよろしくお願いいたします。まずは、IPの重要性について伺いたいと思います。近年ゲームを中心にIPが映画やアニメ、グッズなど様々な形で展開されるようになってきましたが、クリエイターとして、川勝さん自身はIPが広がっていくことをどのようにお感じでしょうか。
川勝氏:IPを広げるということは「ファンの方と一緒に育てていく」ところが大きくて。『グノーシア』を開発している時も最初は全然知られていないゲームでしたが、1人ずつ人が増えていって、一緒に大きく育てていくという考え方で広めていきました。
今回のアニメ化や他機種への展開などは、「ひとつひとつ段階的に広がっていく様を、皆様と一緒に見て楽しめたらいいな」という位置付けで考えています。
IPの重要性としては、「IPはクリエイターを助けます」ということが言えます。ある程度売れてIPが認知されると2つの良いことがあって、ひとつ目は、コラボなどでは必ず原作者の意見が尊重がされたり、最終的なジャッジを原作者に委ねられたりと選択権を持てるようになる、ということです。
もうひとつは、収益の構造として、1本売れたら1年だけでなく、2年目も3年目も広がりとともに収益が上がっていくので、次の新しい開発の資金にとても有効になることです。

ハタノ氏:ありがとうございます。水谷さんはパブリッシャーの立場から、IPの持つビジネス価値をどう捉えていますか。
水谷氏:我々はゲーム販売をしている立場ですが、最近はゲームの消費のされ方としてゲーム実況がありますよね。「ゲームを全然遊ばないけれど、実況動画で見たから『グノーシア』が大好き!」という方がいる状態になっているんですよ。
ビジネス的な話で言えばやはりゲームを売りたいですが、「ゲームを買ってないけれど好きな方」をどうお客様にするかを考える時代になってきています。グッズを出すことで、そうした方たちも買ってくれることもありますよね。
また、ゲームを購入する方が「『グノーシア』を10本買いたい!」くらい大好きでも、やっぱり1人1本ですから、タイトルの価値を最大化してビジネス的に大きくしようと思うと、いろいろなことをしていく必要があります。ビジネス的観点からすると、今はIPの拡大が必要不可欠になってくるかなと思いますね。
ハタノ氏:僕もゲーム実況には馴染みがありますが、ゲーム実況の広まりによって、インディーゲーム業界もビジネス構造が変わっているのですね。
水谷氏:以前はゲーム雑誌やテレビCMでしかゲームの情報が見られなかった時代もありましたし、当時はそこに資本を投下しないと「宣伝もされない、知る機会もない」状態でしたよね。
今はSNSやゲーム実況という、異なる(知るための)パスができて、むしろそちらからの影響の方が大きくなってきています。そこに合わせて、ビジネスを変化させなきゃいけない時代なんだろうなと思いますね。

◆「できることからやっていく」うちにアニメ化へ
ハタノ氏:続いては実際にIPの拡大にあたって、「どう広げていくか」についてお聞きしたいと思います。川勝さんは、ゲームのコンセプト設計の時点で将来的な展開を意識するようなことはありますか?
川勝氏:ゲームの中身によって変わってくるのですけれども、IPを広げていくにあたっては「キャラクター」がとても重要な要素になってくると考えています。
そのキャラクターをどうやって育てていくかを思案すると、ちゃんとした設定だったり、世界観だったりも必要になりますが、あまり世界観をゴリ押ししすぎると、世界観でお腹いっぱいになってしまうことも(笑)。セリフを聞いて、そこにいるキャラクターたちが「きっとこういう育ち方をしたんだな」と垣間見えるような、あくまでもそのキャラクターを通して世界観や舞台を感じられるようにしています。
また、ゲームデザインの仕組み上、本作ではキャラクターの思考次第で人狼ゲームの展開が変わるのですが、ほとんどの場合は同じ手順で遊んでも展開が変わります。いわゆる“消費されない物語”やドラマ性を『グノーシア』に感じたり、世界観やキャラクター性を理由に広まっていったんじゃないかな……と思っています。

ハタノ氏:キャラクターの会話や性格といった部分に、魅力を注ぎ込んでいるようなイメージでしょうか。
川勝氏:そうですね。例えばプロ野球やサッカーは毎年同じルールの同じゲーム大会をやっているのに、なぜたくさんの人が熱狂するのか。それはドラマ性があるからだと思っています。予定調和ではない、その時にしか起きない一期一会の展開がスポーツでは魅力なのではないかと。
それと同じようなことが、『グノーシア』の中でも起こっていると思っていて。このタイミングでこのキャラクターがセリフを言った、話した、助けてくれたことが「私だけにしか起こらなかった」という思い出になる仕組みが、ゲームデザインの中に組み込まれている。
ハタノ氏:確かに『グノーシア』は最初からパラメーターが細かく設定できるので、唯一無二の感覚になりますね。
川勝氏:あとは「必要以上に語らない」というのもありまして(笑)。パラメーターを表示しているのはお客様に分かって欲しいデータだからなのですが、それ以外にもたくさんの情報が裏に隠れています。最初から「このキャラはこうですよ」って全部解説されると冷めてしまうこともあるでしょうし、魅力が低下するんじゃないかなというのもあり、それらは意図的に隠していました。
ハタノ氏:何が起こるかわからないライブ感を演出するだけあって、開発にはものすごく時間がかかったのでは?
川勝氏:4年かかりました。よくメディアでも「4年間で6,000回のテストプレイをした」という話をしているんですけれども、この話をする理由は「どういう思いでそのゲームを作っているのか、どういう人に向けて遊んでもらいたいのか」をちゃんと伝えるべきだと考えているからです。開発者自らがその考えやスタイルを話すことで、ユーザーの皆様にどういうゲームなのかを理解して、安心していただけるのではないかなと。
なので、開発中の4年間には、面白いエピソードがあったら「これは後からお話できるかもな」と全部メモを取るようにしていました。

ハタノ氏:かなりのメモがあるのでは?
川勝氏:結構メモってますが、言えない話が多すぎるので(笑)。ただ、テストプレイの話とかは実際に開発中にやってきたことが皆様に伝わればいいなと思って、使いました。
ハタノ氏:確かに、「6,000回テストプレイしました」というエピソードは、ゲーム実況を主に見ているライト層にとっても定量的に大変さが分かるので、クリエイターさん自身が発信することにすごく価値があると感じます。
では、他のメディアへの展開の計画を考えるとき、パブリッシャー目線ではどのような戦略を考えているのでしょうか。
水谷氏:あんまり計画してた訳では……。逆に、川勝さんは『グノーシア』ってアニメ化しようって考えてました?
川勝氏:思ってるわけないじゃん!(笑)。ないですよ。開発の後半戦にあたって「これ、いつかアニメになったら良いよね」って仲間たちと話した記憶はあります。それだけキャラクターについて思い出を持って作っていたので。
水谷氏:メディア展開も正直あまり考えていなくて。やっていることとしては、ゲームの魅力を伝えていく上で、先ほどのクリエイター自身の話をするとかですね。『グノーシア』で言えば、やっぱりキャラクターが魅力的だったので、キャラクターたちを人に知ってもらう、見てもらうことを優先していました。
プチデポット所属のことりさんにイラストを描いていただいて、それを使っていくのが『グノーシア』を展開する上では有用であろうというのは、発表してからユーザーさんの反応を見て感じていましたね。「これが求められていて、このゲームはイラストが魅力だから伸ばしていこう」の延長線上として、「じゃあアニメにしたら面白いね」という話が繋がってきたのかなと。
本当にその都度状況を見ながら、まずはできるところからやっていくうちに育っていった、という感じだと思いますね。

川勝氏: 『グノーシア』は最初、PS Vita向けに発売したのですが、リリースする2か月前に「Vitaの生産が終わる」ってアナウンスがあったんですよ。(※2019年3月にVita全モデルの生産が終了。同年6月20日に『グノーシア』がリリース。)
水谷氏:そうそう。僕もソニーさんからその話を聞いて、「僕の友達がまだVitaでゲーム作ってるのですが、大丈夫でしょうか」って言いました(笑)。
川勝氏:そのままリリースするわけですけれども、そもそもVitaで発売するとアナウンスをずっとしていた以上、急にほかのゲーム機に移植しますというのはVitaでの発売を持っていたお客さんに失礼だということもあり、ブレずに約束を守りました。販売いただいたメビウスさんには本当にお世話になりました。
あと、基本的にインディーゲームって大体上手くいかないので、ピンチだらけなんですよね。大事なのは、上手くいかないことを「上手くいかない」と思わないことなんです。各方面から心配されましたが、発売した2019年6月は元号が平成から令和に変わった直後だったので、「平成最後のVitaゲー」「令和初のVitaゲー」みたいな冠が付けられて、また注目を集めました。
ただ、Vita版のみだと遊べない人も多くて。SNSやブログでしかどんなゲームか分からないけれど、一部のユーザーが盛り上がっている。でも遊ぼうと思っても遊べない……みたいな状況があり、さらにファンの皆様からも「Vitaだけで終わらせるな」という要望がすごく多かったので、じゃあ他プラットフォームへ移植しようということになりました。
我々の方からこうしようという意図もあったはあったんですが、最終的にはお客様の要望で展開していったということなので、ファンの皆様のおかげですよね。
ハタノ氏:なるほど。ファンとともに成長してきた分、メディアミックス化のタイミングは難しかったのではないかと思いますが、計画の立て方はいかがでしたか。
水谷氏:そうですね。今回はアニメ化が我々も初めて経験することだったので……何年ぐらい制作してましたっけ。
川勝氏:これも4年ぐらいかかってますよね。
水谷氏:ということは「4年後も『グノーシア』が盛り上がってる状態にしなきゃいけない」プレッシャーがすごいありましたね(笑)。令和最初のゲームで盛り上がっていたのに、それを現在までファンが途切れないよう話題を作り続けていかなきゃいけないって、ちょっと必死だったかもしれないですね。

川勝氏:でも、「1年単位でこれはしておこう」と、ある程度の見通しは立ててやっています。毎年1プラットフォームずつ、ニンテンドースイッチへの移植が終わった次の年には新しいゲーム機に移植するとか、また次の年にはSteamに出すとか、1年単位で計画をしていました。
その後にグッズですね。「グッズ化したいです」とオファーしてくださる会社さんがいくつかあったので、そちらと一緒に組んで作るのですが、基本的に需要と供給のバランスがおかしくて……お客様の需要に対して供給が全く追いつかない。
人数が4人しかいないからできないこともあったので、本当に年に1回ぐらい、グッズ化をやらせていただくように考えていました。そこで大事にしていたのは、「グッズをそのメーカーに委ねない」ということ。IPを貸すので「好きに作ってください」ということはせず、直接メーカーさんと一緒に「こうしましょう」「これは売りません」とか、かなり細かいところまで入って作っていきました。
発売するにあたって、プロモーションのひとつとして、原作者の私が直接入って「こういう思いですよ」と示しながらグッズを作っています。普通ではやらないだろうことでも、自分がお客さんだったらそうしてほしいことを自分でやろうかなと。
水谷氏:大前提として、ゲームのIPと呼ばれる知的財産は、一般的にはお金を出した人のところに紐づくケースが一般的な事例です。でも、パブリッシャーが企画して制作いただいた場合は、作った人ではなく、最初に企画してお金出した人のところにIPがつくんですよ。
インディーゲームは基本的に制作者にIPが残るんですが、今インディー界が盛り上がってくる中で、「IPを半分持たせてください」みたいな投資家や、我々みたいなパブリッシャーも増えてきています。
僕はクリエイター大好きというか、物を作る方への尊敬みたいなものが人よりもあると思うのですが、やっぱり「『グノーシア』を作った人がこれを生み出しました」とグッズも含めてちゃんと責任持って全展開やっていくというが大事。川勝さんは、これをずっとされてきていていると思います。IPを保持することは、インディーゲームにとってすごく重要なポイントです。
ハタノ氏:やっぱり、キャラクターの性格に合ってないようなグッズが作られてしまうとかがありますか。
水谷氏:そうですね。作品の世界観が増幅されてのグッズであれば良いのですが、世界観から外れたことをすると、一番敏感なユーザーの熱が冷めてしまいます。望んでないものが出てきて、熱を下げないようには気にしていると思いますね。