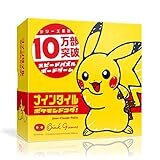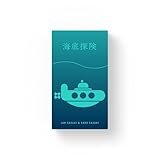先日放送された「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2025.7.31」にて、突如発表された新作ソフト『チルっと焚き火ソン』。どうやら焚き火を育てるシミュレーションゲームのようで、ニンテンドースイッチ2の「ゲームチャット」を活かして一緒に焚き火を育てることもできるようです。
販売はボードゲームで有名なオインクゲームズ。一時はニンテンドースイッチ2のダウンロードソフトの5位に登場するなどジワッと人気を見せているようですが、1,650円というやや強気な価格もあり、買うか悩んでいる人も多いかもしれません。本記事では、実際に本作を買ってみてどんなゲームだったのか、そして「コミュニケーションツールとしてはどうなのか?」といったところも紹介していこうと思います。
薪ごとに温度と水分量のステータスを持つ本格焚き火シミュレーター
『チルっと焚き火ソン』には、無限湧きする薪で焚き火を育てることが目的の通常のモードと、限られた焚き火でより長時間の燃焼を目指すスコアアタックのような遊びの「サバイバル」モード、そしてマルチプレイ時に別々の焚き火台が用意される「プレイグラウンド」モードの3種類の遊び方があります。

ゲームを最初に開始した時には通常のモードのチュートリアルが開始。このモードでは、焚き火を成長させ「焚き火レベル」を10以上にすることが目的のようです。
まずは近くの薪を「ナタ」で割って細かくし、着火剤の上にのせて着火します。しばらくすると乗せた薪が燃えるので、次にもう少し大きい薪を用意してその上に乗せます。このように、薪が燃え尽きる前に世代交代し、だんだんと薪を大きくしていくことでレベルを上げていきます。

「焚き火センサー」というアイテムを使って薪の状態を見てみると、薪にはそれぞれ「温度」「水分」「酸素」「太さ」というステータスが割り振られていることがわかります。この温度が300度に達するとその薪に火が燃え移り、燃焼がはじまります。
薪は太いほど長く燃焼しますが、その分温度が上がりにくいです。逆に細い薪は燃え尽きるまでの時間が早い分、温度が上昇しやすくなっています。基本的にはこの特性を活かし、火が燃え尽きないように適度に細い薪を入れながら、太い薪に十分な時間を与えて燃焼させ、段階を踏んで焚き火を育てていくというサイクルのゲームとなっています。
水分は薪の温度が100度になると蒸発し始めるのですが、その時発生する水蒸気は周囲の熱を奪います。全て蒸発しきって水分が0%になると温度が再び上昇し始めるようになっています。薪の燃焼には酸素も必要不可欠で、薪を隙間なく積んでいくと酸素不足になって燃焼が止まってしまいます。

さらに、同じ薪でも時間とともに燃焼していた部位が炭化していき、燃焼する場所が変化していきます。周囲の温度も薪が燃えている部位に応じて移動していくため、他の薪を燃やすためには薪が燃えている場所も考慮する必要が出てきます。「火吹き棒」を吹くことで、その部位の燃焼を早め、周囲の温度を上昇させるテクニックも重要です。このように、ただ闇雲に薪を積んでも焚き火を育てるのは難しい、本格的なシミュレーターになっているのです。
ですが、それは高難度な“後半のステージ”での話。このゲームには「砂浜」、「林」、「高原」、「雪山」と4つのステージがあるのですが、最初に訪れることになる「砂浜」に関しては、そこまで高度なことは考えなくてもなんとなくで焚き火を育てることが容易な作りになっています。砂浜に落ちている薪は元々水分量が少なく、気温が低い「雪山」や雨の降る「高原」のように焚き火の成長を妨げる要素がないからです。「雪山」や「高原」で焚き火を育てる難易度はかなり高く、しっかり熱や水分の管理をしないとすぐに火が消えてしまいます。

つまり、タイトルのように「チルっと」焚き火を育てる時間にしたい時は「砂浜」のステージを、より高度な管理が求められるシミュレーション的な歯ごたえがほしい時はそれ以外のステージを遊べばよいということ。これは、マルチプレイの時にも同様のことが言えます。
焚き火の前で友達とゆったり過ごすか、焚き火をめぐる攻防を繰り広げるか

『チルっと焚き火ソン』はゲームチャットを介した最大4人のマルチプレイに対応しています。ゲームチャットに招待した、ゲームを所持している友達と一緒に焚き火を作れるほか、ゲームを所持していない友達とも「おすそわけ通信」を使えば遊ぶことが可能です。
上述したすべてのモード、ステージでマルチプレイが可能となっていますが、ゆったり過ごすなら上述のとおり難易度の低い「砂浜」ステージがおすすめ。本作には、焚き火のレベルに応じてトークテーマを表示する機能が搭載されていますが、高難度なステージは忙しいのでテーマについて話している暇はあまりないかも。

「プレイグラウンド」では焚き火台が4つ設置されており、それぞれの台で焚き火を作ることができます。要素はただそれだけですが、たとえば「どちらが早く焚き火レベルを10にできるか」を競い合ったり、「サバイバル」のように限られた薪でどれだけ長く燃焼させられるかを競ったりと、プレイヤー自身がルールを決めて遊ぶことができます。
相手の台の薪を横取りしたりといったことも自由なので、どこまでが反則でどこまでがルールなのかといったことも決めておくとより楽しめます。筆者の場合は、「焚き火のレベルが上がったら相手の薪を1つ取っていい」というルールで遊びました。

このように、ゆったりと焚き火を前にチルな時間を過ごす楽しみ方と、高難度シミュレーターを攻略する楽しみ方の双方ができることが本作の魅力です。
本格的な焚き火シミュレーターをベースにいろいろな遊びができるゲームになっているものの、1,650円という価格分を回収するにはかなり前のめりになって楽しまないといけないというのが正直なところです。これを友達に「一緒に遊ぼう!」といって買ってもらうのは申し訳なさが勝ってしまう。
本作はオインクゲームズがリリースしていることもあり、「だれか1人が買ったボードゲームをみんなで遊ぶ」というような楽しみ方を「おすそわけ通信」ですることを想定したゲームなのかもしれません。