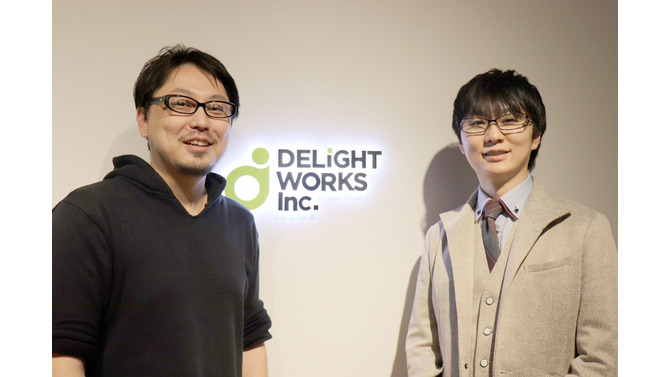◆現役だからわかる教壇に立つメリットと業界が抱える問題
――現役クリエイターとして教壇に立つメリットはどこにあると思いますか。
塩川:
まず人に教えるというのは自分にとってもプラスになります。自分が考えていることを人に伝えるには、体系化して、かつ相手に理解できるようにまとめなければならないので、自分が今まで考えてきたことは何だったのかを整理することができますし、これは自分にとっても大きな成長が期待できるのではないかなと思います。
また、現役の人間が教えるという事は意味があると思います。まず意外だと思われるように、現役クリエイターが教壇に立つケースは少なく、ことゲームの企画やディレクションに対してはほとんど例がありません。
私がかつてアメリカに出向していたとき、現地のクリエイターたちが専門学校に出向き積極的に教えている姿を目撃しました。当たり前のように学生に教えに行くことで育成を体系化させていました。また、学生と切磋琢磨して、ゲーム業界を発展させてきたのだと感じました。私ひとりがやったところでどうなるかわからないですが、この試みからゲーム業界の人材をひとりでも多く育てていけたらと思います。特に私がやっているディレクションという分野は人を育てるという事が体系化されていないジャンルなので、私が教壇に立つことでそれが少しでも進めばいいと思っています。

――糸曽教授は実際に現役クリエイターの教授であるわけですが、そのメリットはどうですか。
糸曽:
私は美術系の大学に行ったのですが、そこで学びたかったのはエンターテインメントでした。地方出身でインターネットもない時代だった人間には現場の仕事なんて想像つかないですから。専門学校では現役の方を招いて実践的なことをされていると聞いて、自分が大学の時にそういう機会があればよかったのにという気持ちがありました。
私のところに7年前に大阪成蹊大学の門脇教授(現芸術学部長)からコンタクトがあり、教壇に立つようになりました。学生時代に感じたことを踏まえ、「現場を離れない」ことを条件に受けさせていただきました。また、私がお世話になり始めた頃から京都や大阪にアニメーション会社ができ始めたので、外部講師としてスタジオのクリエイターを招き、スタジオと長期のインターン提携をして卒業後はそこに学生を就職させることもできました。学校も就職率があがるし、学生も現場で学べる、スタジオにとっても時間をかけて信用のできる学生を選出できる。双方にメリットのある形を作り出すことができたのかなと。そういった試みを増やして就職率100%を実現したときに、私が大学にいる意味はあると感じたんですね。
実はそういう試み自体が関西の大学では少ないのです。かつて業界にいたという教授はいます。こういう言い方が正しいかはわかりませんが、ドットのゲームを作っていた方にVRのゲームを教えてくれと言ってもそれは難しいかなと。大阪成蹊大学はアニメ・マンガ・ゲームの現役のクリエイターを多く教員に招いて実践的な教育を行っていますが、今の業界はどうなっているのか、今は何が求められているのかを教えられる先生がもっと多くいるといいなと思った時に、塩川さんに出会ったというわけです。
――塩川さんはこれまで技術者に向けたセミナーなどもされてきましたが、大学では18歳くらいの学生に教えることになります。そのことについてどのように感じていますか。
塩川:
やったことがない試みなのでチャレンジではあります。自身に課しているのは、「継続的なことをやった結果、何につながるのか」ということです。1年間教えたことで学生さんが何を得るか、そして私自身がどんなことを学べるかが自分の中の大きなチャレンジですね。
――どのような人材を育てたいという明確な目標はあるのですか。
塩川:
そこは明確な目標があって、「考えることができる人」になってほしいと思っています。目指す仕事が何であるかは関係なく、ものを作るときに「何のために作るか」「誰の為に作るか」「どんな成果を得たいか」の3点を考えられるようになってほしいですね。当たり前のことなのですが、これが自分の中で成立している人はプロの中でも多くはありません。
――それがクリエイティブ業界全体の危機感としてあるということでしょうか。
塩川:
そういう人材が少ないとは思います。学生と対話をしてきた中でもそう感じましたし、元々大きな会社にいたのでその中でもそう感じました。すごい技能を持っている人はいるんです。でも先ほどの3つをセットで考えて仕事をする人が非常に少ないなと感じます。私は、これができる人を増やしたいと思っています。
学生から企画書をみてくださいと言われる機会があるのですが、それを見て思うのは「君は本当にこれが作りたいの?」ということ。「授業でこういう課題があったから」とか、「就職活動で使わなければならない」とか、そういう理由で企画書を書いているわけです。でもそのような理由で書かれたこの企画書にいったい誰が共感するのでしょうか。プロになったら同僚や上司の心を動かさなければならない。その先にお客さんがいるわけです。課題であっても見る先はお客さんじゃなきゃと思うのです。
そこで私がやらなくてはならないのは、熱意のこもっていない企画書にに熱意を与える技術ではないかと思うのです。彼らが自分たちで熱意を入れることが当たり前だと思っていただけるようになればよいかなと思います。そもそも課題に熱を入れなければならないという発想が抜けていると思うんです。そういう概念から教えたいと思いっています。そうすれば次の課題で同じことはしないはずです。
◆歯車になるか、それ以外の人生を歩めるようになるか
――ほかにもクリエイティブ業界について対して懸念されていること、クリエイターを育成するにあたっての問題などあれば教えてください。
糸曽:
今は世の中が便利になって、努力する必要性がほとんどなくなりました。アニメーションでも努力シーンを入れるとお客さんが離れてしまうのでカットする傾向にあります。昔の恋愛シミュレーションゲームだったらひとりの女の子を口説くためにめちゃくちゃ努力をし、それが達成感としてあったのですが、最近は逆に女の子は全員自分が好きで、自分に選ぶ権利がある。つまり、最初から翼があって飛べる状態なんですね。
それが当たり前になっている時代の学生たちに向けて、我々の世代がどう歩み寄って学んでいただくか。そこを考えていかなければならないと思います。自分が学生の頃、「最近の若い奴は」と言われて突き放されるのがとても嫌でした。常識なんて世代ごとに変わっていきます。だから私自身も学生から学びつつ、カリキュラム構築をしています。

彼らは我々の世代をヌルイと思いつつ歩み寄ってくれていたのだと思います」と語る糸曽教授。
塩川:
翼の話を別の言い方で置き換えると、ゲーム作りでいえばUnityやUnreal Engine4という便利なツール、つまり付けられる翼があるわけです。
また、スマートフォンのゲームは規格化、フォーマット化が進んでいて、ある程度のことは考えずに規格通りにやれば形にすることだけはできます。これもある意味、翼です。いい面としては参入障壁が下がっています。チャンスもいっぱいあります。ところがどこかで越えられない壁にぶつかってしまいます。そういう人がゲーム業界に増えていくと、ゲーム業界全体で作れるものの限界が見えてしまう。
そして規格化が進んでいくと起こるのは、プロダクションバリューや物量勝負になることと、続編や有名なIPありきで勝負することになります。そこでは思考や工夫があまり必要なくなってきます。お金と資産が決め手になるためです。自分が努力して何かを生み出したり、その状況を作り出したという体験をする機会も減ってきています。
そうなったときにどう行動するかが問われる。言い方が悪いかもしれませんが、歯車になるか、そうではない生き方を見つけるか、です。これからゲームクリエイターを目指す多くの人が、知らないうちに歯車になってしまうのではないか。そういう未来に対する危機感はありますね。
――今からやれば遅くないという思いがあり教壇に立とうとしているのでしょうか。
塩川:
そこまでの確信はありませんが、誰かがやらないと。嘆いていてもしょうがないですから。私は欧米のAAAタイトルを作るようなマーケットにいたことがあるのですが、そこでまさに同じことが起こっていました。1つのゲームタイトルに何百億かけれないとエントリーができない状態になっており、エントリーの壁がどんどん上がっていた。プロダクションバリューを上げてお金をかければ、他がついてこなくなる。勝っている人はさらに勝つ、というわけです。
一方でメジャーなクリエイターたちは大企業の歯車になることを辞めてインディーズに行きました。だから欧米にはクオリティの高いインディーズゲームが多い。歯車か、そうではない生き方か。今の日本のスマートフォンゲームもいずれは同じことになると思います。歯車の頂点を目指すのもひとつの目標ですし、それを楽しいと思ってやるのは個人の考え方ではありますが、私が人に教えていく中では、そういう現場でどうやって個性を出していくかを教えていきたいと思うのです。そういう思考ができる人に巡り合いたいですし、できればそういう人と一緒に仕事をしたいなと思います。

糸曽:
今の話で思い出したのですが先日視察した海外の有名アニメスタジオでも同じ現象が起こっていました。お金をかけてどれだけ効率よく作るかなんですね。一方でそのスタジオを辞めてインディーズでやっている方ともお会いしたのですが、組織が大きくなり効率化を図るようになったら自由がなくなってしまった、もう私のいる場所じゃないと思って辞めたそうです。クリエイティブな業界に身を置きながらどうやって自分の居場所を作るのか。長くやっていく上では重要なことだと思います。
塩川:
大きな組織の中でエキスパートになるのも大事だと思いますが、そうした中で、自分が主導権を持って選択肢を選ぶ側にいられる方がよいと思います。これから客員教授として学生さんに教えていく立場になるわけですが、「考えること」を教えていきたいですし、学生さんには選択肢を持つ側になってほしいと思うのです。
―――塩川さんの今後の予定について教えてください。講演等はこのまま続けて行くのでしょうか?
塩川:
自社の勉強会もそうですし、専門学校への講義などは続けていこうと思っています。ただ自分にとって教授と言うのは新しい挑戦なので、これをやりきるという事が第一だと考えています。あとはこういった試みは単純に面白いですよね。自分のクリエイティブの業務に好影響になると思います。クリエイターは面白いことをやるのが仕事なので、こういう試み一つとっても面白くしたいんです。
―――確かに、面白いというか、まずは驚きました。「忙しいのに大丈夫なの?」という意見も多いのではないでしょうか。
塩川:
それも含めて「えっ!?」と驚いてもらいたいわけです。我々は人の心を動かす仕事をしているわけですから、人の心の動かし方を忘れてしまうと良いものができなくなってしまうんです。そういう意味でもこの試みを面白い、と思ってもらえたらスタートラインとしては上々ですね(笑)
この記事を読んだ方は「なんで塩川が大学で教えることを選んだのか」について知りたかったと思うのです。そしてもし自分の所属する業界の人材育成に対して危機感を持っているならば、「自分だったらどうするだろう」と考えてほしい。それこそ、ゲーム業界の現役クリエイターの方がこの記事を読んで「自分もやろうかな」と思ってくれたら嬉しいですね。「塩川が教えるくらいなら」という感じで腰を上げてくれて、それによってゲーム業界全体が活性化すればいいのではないかと思います。それにはまず誰かが行動を起こすことが大事だと思うのです。
―――ありがとうございました。