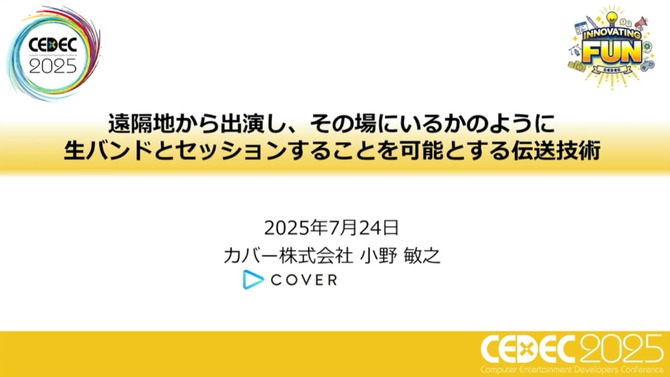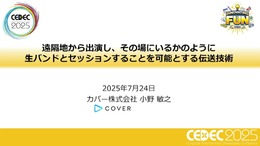ゲーム技術者やコンピュータエンターテインメントのエンジニアらを対象とした国内最大級のカンファレンス「CEDEC 2025」が、2025年7月22日から24日かけてパシフィコ横浜 ノースにて開催されました。
24日にはカバー株式会社のクリエイティブ制作部で活動する小野敏之氏による講演が実施。小野氏は、ライブ会場にて演奏している生バンドにあわせ、会場から離れたスタジオから生歌唱・生出演を行なうことを可能にする技術について解説しました。

小野氏は2023年にホロライブ株式会社に入社し、クリエイティブ生産本部配信技術部へ配属し、現在まで配信業務の技術者として携わってきました。現在は撮影チームとスタジオ設備チームを統括するマネージャーとして活動しています。
撮影チームはカメラマンとスイッチャーというオペレーターが所属している部署になり、スタジオ設備チームはスタジオの映像、音声、モーションキャプチャー、スタジオの映像音声システムを実現するための大規模ネットワークまで、スタジオ機能と配信システムのアップデートやメンテナンスを行ないます。このセッションは、後者のスタジオ設備チームにまつわる講演会になります。
小野氏によれば、現在ホロライブプロダクション所属のタレントはテレビ出演や各種イベントへの出演機会が増えているそう。そうした出演オファーにおいては、通常は現地にモーションキャプチャーシステムを構築して対応していますが、会場の物理的な都合であったり、電源確保の問題、実施するために十分なセッティング時間が取れないといった問題があり、出演をお断りしていることもあるといいます。
ファンのみなさんが喜んでもらえるようなチャンスを失ってしまう。こういった機会損失を減らす手段として、伝送技術をアップデートすることで解決しようと取り組みが始まりました。

このセッションでお話する「伝送」というのは、映像と音声をある場所からある場所へと伝達することだと小野氏は解説します。
例えばスタジオをA地点、イベント会場をB地点とした場合、A地点からB地点へ向けて映像と音声を片方向で届けるというものです。有名なところで例えるならば、配信を行う際には配信場所となるスタジオや自宅から、配信プラットフォームのサーバーまで、映像と音声のストリーミングを送出していることを指します。
配信拠点からサーバーまでは伝送、サーバーから不特定多数に向かって流すのは一対多数という形になるので配信または放送といった名称になります。ネットワークの世界でも、送り先を指定して1対1で行われるデータ通信のことをユニキャストと呼んだり、一対複数のデータ通信のことをマルチキャストやブロードキャストなどと呼んだりしています。


この記事を読む読者や普段から配信プラットフォームをご覧になっている方はよくご存知かと思いますが、伝送や配信にはどうしても遅延がつきもので、避けて通れない壁になっています。視聴者目線ですと、生配信中にコメントしたりメッセージを送っても数秒遅れでリアクションが返ってきます。これは、遅延の仕業と小野氏は指摘します。
今回の想定している「現地にいる生バンドの演奏に合わせて歌唱する」というチャレンジでは、このような遅延が起こってしまうと、歌唱するタイミングがズレてしまい、生バンドとのセッションは到底実現することができません。そもそも、伝送が途切れてしまっては大きなトラブルとなってしまうため、安定した伝送が行えることも当然不可欠です。
音の遅延を極限まで減らしたうえで、遅延の揺らぎすらないほどに安定した伝送を実現しなけれなばならないと小野氏は解説しました。

一般的に普及している公衆インターネット網を利用した映像音声伝送を使用した場合、伝送帯域が十分に確保できなかったり、時間帯によっては帯域が低下してしまったり、ネットワークに揺らぎがあったり、パケットが詰まってしまったりと、様々な不安要素がつきまといます。
公衆インターネット回線は自動車の道路のようなもので、さっきまで1Gbps近い回線速度が出ていたはずなのに、急に100Mbpsくらいしかでなくなったりすることを体感した方がいるかと思います(筆者も感じたことがあります)。
小野氏はこういった現象を、対面式の車がギリギリ1台通れるくらいの細い道路に例えました。回線速度が安定せずに速くなったり遅くなったりという揺らぎがある状態は、ストレートの道路の先に急にきついカーブが出てきて、速度を落とさざるを得なくなった状況だそう。
強力なエラー訂正技術を利用することで安定性を向上させることもできますが、エラー訂正を強くすればするほど通信帯域を増やす必要が生まれますし、そもそも伝送の遅延を増加させてしまうなどの代償が生まれます。
つまり、一般的なインターネット回線を使った伝送方法を使おうとすると、伝送が途切れてしまうリスクが伴ってしまうといえます。


ではこういった課題に対して、どのような解決策を編み出したか。小野氏はシステム系統図とともに解説していきました。

図面の上半分がスタジオのシステム、下半分が現地のシステムになります。
スタジオ側には、AV over IPのST2110をベースにした映像システムと音声システムがあり、IP Gatewayと呼ばれる機器を使ってIOとベースバンドのコンバーターも置いてあります。すべての映像機器がST2110に対応しているわけでないため、このようなコンバーターが必要になってきます。
会場側にはステージ、モニターに映すための映像システム、それに付随したPAシステムがあります。会場の様子がわかるようにカメラをおいたり、観客の声を拾うマイクも設置しています。
この図面でぼかしているところが、今回のお話の要になる超低遅延を実現する伝送技術の部分になっています。
先にあげたように、公衆インターネット網は回線の品質や調子が良いときは問題は起きませんが、時間帯や揺らぎに遭遇すると、ブロックノイズや音声ノイズが生まれてしまいます。古くからある電波を使用したり通信衛星を用いた伝送も検討されましたが、ホロライブの事業内容からして免許を取ることはできなかったと振り返ります。
検討を重ねて小野氏とカバーが目をつけたのは、ダークファイバーを用いた非圧縮での映像音声の伝送でした。

システム図の真ん中にピンクで囲った部分がありますが、ここではスタジオと会場を結ぶ回線構築にダークファイバーというものを用いています。
ダークファイバーとは、日本全国に張り巡らされた光ファイバー網のなかで、通信事業者が普段は使用していない部分、将来需要が増えた場合に備えて持っている予備・未使用の光ファイバーのことを指しています。このダークファイバーを使えば、光ファイバーの圧倒的に広い通信帯域を余ることなく利用することができると小野氏は解説します。

通常のインターネットを利用した伝送は、通信帯域に収まるように圧縮と呼ばれるエンコードを行なったうえで送られ、受信側では圧縮された信号をもとに戻す復号と呼ばれるデコードが行なわれます。前述のエラー訂正に加えて、このエンコード、デコードでも遅延が生まれてしまいます。
一方、ダークファイバーは通信帯域が圧倒的に広いため、圧縮をすることなくそのまま伝送できるわけです。エンコード、デコードの流れもないので、遅延が発生しません。

また光の波長を信号ごとに変えることで、1本の光ファイバーに多重にして同時伝送することも可能になっています。スタジオ側、現地側に光ダークファイバーで繋がれた装置がありますが、こちらはWDMと呼ばれるもので、光を多重にしている装置になっています。名前はWevelength division multiplexingの頭文字をとっています。

この1本の光ダークファイバーを使って、生バンドの音声信号やお客氏の様子を映すカメラ映像を会場から送り、タレント本人の映像と音声をスタジオから送れるようなシステムを構築したそう。
伝送の安定性も、このダークファイバーを利用することで解決しています。スタジオと会場間ででしか使用していいない専用の線なので、他者が介入して混雑したり、帯域が狭まることが起こらないので、非常に安定した伝送をすることが可能になったといいます。
このダークファイバーを使用した帯域を確保したことにより、会場側での回線速度や通信帯域に悩まされることも一切なくなり、スタジオとイベント会場とを別経路の光ファイバー2本で結ぶことで、予期せぬトラブルが起こった際にも迅速に対応ができるようになりました。

参考程度に、カバーのスタジオから音声信号を送り、遠く離れた場所でループバックさせ、スタジオへと戻ってきた信号のち塩を測定してみたところ、遅延は1msec未満で、体感上ではまったく遅延を感じないレベルとなっていたそう。ダークファイバーによる伝送がいかに超低遅延なのかが伝わります。

このように伝送回線の遅延を極限まで抑える道筋はできましたが、収録や伝送にはST2110のベースバンドを使用したハイブリッドなシステムで日々制作を行なっており、この制作環境から、スイッチャーによるシステム遅延があったり、IP Gatewayを使用した際にも遅延が起こってしまいます。
つまり通常の配信システムをそのまま使ってしまうと、生バンドとのセッションをする際に影響が出るほどの遅延が伴います。
そこで、映像と音声をいったん切り離してシステムの見直しが行われました。システム図にあるように、光ダークファイバーの直前と直後にMUX、DeMUXを配置しています。MUXとはマルチプレクサ、DeMUXとはデマルチプレクサのこといい、2つ以上の入力を1本の信号として出力したり、分離する装置のことです。直線、直後にこの装置を置くことで、変換遅延を考慮せずに伝送経路に載せることが可能になります。
映像に関しては現地会場側のスイッチャーやLED装置など、遅延を増加させてしまう要因がいくつもあります。そのため、現地にいるPAにはダークファイバーを通ってきた直後にDeMUXして音声と映像を切り離し、最小遅延で音声を渡すという系統になっています。
スイッチャー機材の中にもMUXする機能がついているものがありますが、スイッチャーの機材も少なからずの遅延が生まれてしまう要因になります。そのためホロライブでは、MUXとDeMUXだけの機能しか持たない単一機材を用意して対応しています。

このあと小野氏は、実際にインターネット網を通した伝送の比較動画と光ダークファイバー網を通した伝送の比較動画で、どの程度の遅延が起こっているかを聴講者に向けて上映しました。
前者は確かに遅れているように見えましたが(0.3秒ほどの遅延)、後者はほとんど遅れがないレベルでの通信ができていました。
下の写真は両者を比較した際のものですが、インターネット網の伝送とダークファイバーを用いた伝送が同時に発信すると、ダークファイバーを用いた伝送だけが受信し、インターネット網を用いた伝送がまだ受信していないことが分かります。
その一瞬後に、ようやくインターネット網の伝送が受信している、という形になっています。
この間は本当に一瞬、ゼロコンマレベルの間の違いなのですが、生バンドとのセッションを可能するための伝送技術として、ここまで到達していないといけないことが伝わります。


小野氏はまとめとして、超低遅延での伝送技術には以下の3つの要点としてあげました。

十分な通信帯域と持ち安定した伝送が実現できる光ダークファイバーを選定し、遅延が増える要因となるシステムや機器を徹底的に排除、システムの中に組み込まないという姿勢が重要だったと振り返ります。
今後もカバーの技術力を高め、進化させ続けていきたいと語り、講演は終了となりました。今後もカバーの技術開発をすすめ、エンタメづくりの基盤をより強固にしていきそうです。