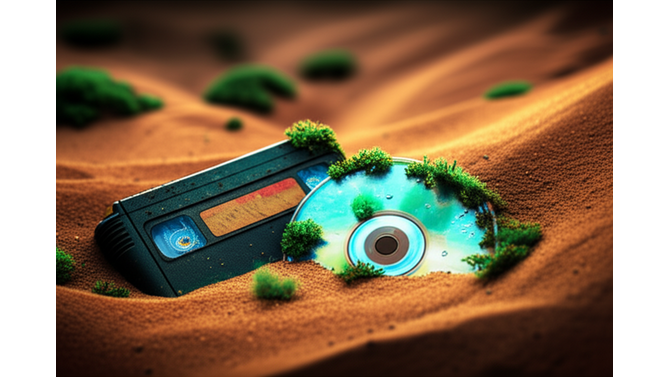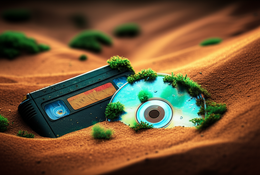過去の名作ゲームを現代のハードで遊びたい。そう願うゲーマーは少なくないでしょう。しかし、移植やリメイク、リマスターといった「ゲームの復刻」には、オリジナル版の権利者の許諾が不可欠です。では、もしその権利者が誰なのか分からなかったり、連絡が取れなかったりしたら、そのゲームは永遠に埋もれてしまうしかないのでしょうか?
そんな「権利者不明の著作物(孤児著作物)」の活用への道を開くのが、文化庁が運用する「権利者不明等の場合の裁定制度」です。この制度は、ゲーム業界にとっても大きな可能性を秘めています。
さらに、2026年度(令和8年度)からは、より使いやすくなることを目指した「未管理著作物裁定制度」もスタートします。これら2つの制度は、今後どのように使い分けられ、ゲーム文化の保存と活用にどう貢献していくのでしょうか。
編集部では、この重要な制度について詳しく知るため、文化庁著作権課著作物流通推進室長の八田聡史氏に直接インタビューを実施。制度の基本的な仕組みから、ゲーマーや開発者が気になるであろうポイントまで、一問一答形式で切り込んでいきます。
「裁定制度」って、そもそもどんな制度?
――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、我々ゲーマーやゲーム開発者にとって重要かもしれない「裁定制度」について、基本的なところから教えていただけますでしょうか。
文化庁(以下、八田氏):よろしくお願いいたします。まず大原則として、他の方が権利を有する著作物を利用するには、その権利者から直接許諾を得る必要があります。
しかし、その権利者と連絡が取れなかったり、そもそも誰が権利者か分からなかったりする場合があります。例えば、作者が亡くなり相続人が不明なケースや、会社が倒産して権利の承継先が分からないケースなどです。
こうしたケースで 、相当な努力を払っても権利者と連絡できない場合に、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する「補償金」を供託(法務局に預けること)することで、その著作物を利用できるようにするのが「権利者不明等の場合の裁定制度」(以下、現行制度)です。
重要なのは、この制度はあくまで「適法な利用を認める」ものであり、著作権そのものが申請者に移転するわけではない、という点です。この点は、新しくできる「未管理著作物裁定制度」(以下、新制度)にも共通します。
新旧2つの制度、何が違う?
――2026年度からは新しい裁定制度が始まると伺いました。これまでの現行制度とは、どのような違いがあるのでしょうか。
八田氏:2023年(令和5年)の著作権法改正で新制度が創設され、2026年4月に施行予定です。これにより、2つの制度が並立することになります。利用者は利用したい著作物の状況や利用方法などに応じて、利用する制度を選ぶことになります。
2つの制度で重なり合う部分もありますが、
大きな違いは、対象となる著作物の範囲です。
現行制度(権利者不明等の裁定の場合):権利者が不明、または連絡先が不明で権利者に連絡がつかない場合が対象です。
新制度(未管理著作物裁定の場合):利用の可否に関する権利者の意思が確認できない場合が対象です。この制度では、現行制度では対象外である、「権利者は分かっていて連絡先も判明しているが、問い合わせても返事がない場合」も対象になりえます。

また、利用できる期間にも違いがあります。
現行制度:法律上の期間の定めはありません。ただし、申請時に利用の範囲(複製する数量など)を明確にしなくてはならず、その範囲を超えて新たに使いたい場合は再度申請となります。
新制度:最大3年間という時限的な利用期間が定められています。3年を過ぎて継続利用したい場合は、再度申請することが可能です。こちらの場合でも利用の範囲は申請時に明確にする必要があります。
――なるほど。連絡しても返事がないケースでも使えるようになるのは大きいですね。申請する側は、どういった基準で制度を使い分けることになるのでしょうか。
八田氏:例えば、新制度は現行制度に比べて手続きが簡素になることを目指しています。一方で、3年という期間の定めがあります。ですので、3年を超えて長く利用したいと考えるなら現行制度、まずはスピーディに利用を開始したい場合は新制度、といったように、利用したい期間や状況に応じて申請者の方が選ぶ形になります。
どんな著作物が対象? 未発売のゲームにも使える?
――どういった著作物が裁定の対象になるのでしょうか。例えば、まだ世に出ていない「未発表・未発売」のゲームはどうなりますか?あるいは権利者不明の素材がゲームに使われていることが発売後に分かった、といったケースでも利用できますか?
八田氏:裁定制度が対象とするのは、法律上「公表された著作物等」と定められています。つまり、すでに世の中に発表されているものが対象です。
これは、著作者が持つ「公表権(自分の著作物を公表するかしないか、いつどうやって公表するかを決める権利)」を尊重するためです。したがって、全く世に出ていない未公表の著作物を、この制度を使って公表することはできません。
また、著作物の公表・販売後に権利者不明の素材の使用が発覚したケースについてですが、裁定制度はこれからの利用を適法にするための制度であり、過去に遡って利用を問題なかったことにするものではありません。その場合は、権利者を探して許諾を得ていただくことが必要で、裁定制度の申請はあくまで今後の利用のためということになります。
海外のゲームや素材にも制度は使えるの?
――海外のゲームや、海外で作られた素材の権利者が分からない、といった場合でも日本の裁定制度は利用できるのでしょうか。
八田氏:はい、外国人の著作物であっても、その著作物の利用が日本国内のみで行われるのであれば、裁定制度を利用できます。
ただし、新制度の場合は少し注意が必要です。外国の著作物も対象にはなり得ますが、連絡先に意思確認を行う場合には、「国内にあると認められる連絡先」に行う必要があります。例えば、海外の企業でも日本法人や日本の事務所があれば、そこが連絡先となりえます。しかし、連絡先が海外のメールアドレスやウェブサイトしかない場合は、適切な意思確認を行えないため、新制度の対象外となります。
――例えば、ゲームをダウンロード販売する場合、一部大手の販売プラットフォーム(Steamなど)の運営会社は海外にあります。この場合、日本国内限定で販売するのであれば利用は日本国内のみと言えるのでしょうか。
八田氏:個別の事案によります。重要なのは「その著作物がどこで利用されるか」という点です。なので、海外で利用・販売する場合は、その国の法律に従って権利処理を行っていただく必要があります。

裁定制度を利用して作った作品の「権利」はどうなる?
――ここが一番気になるところなのですが、裁定制度を利用して、例えば権利者不明のレトロゲームの復刻版(二次的著作物)を作った場合、その新しい作品の権利はどこまで主張できるのでしょうか。
八田氏:大前提として、裁定制度は著作物(元の作品)の利用を認めるものであり、その権利を申請者に与えるものではありません。したがって、著作物そのものについて、排他的な権利を主張することはできません。
例えば、Aさんが裁定制度を使ってある孤児著作物の復刻版を作った後、Bさんが同じ孤児著作物について裁定を申請し、認められれば、Bさんもその孤児著作物を利用できます。先に申請したからといって、後からの利用を妨げることはできません。
――なるほど。では、例えばAさんとBさんが偶然とてもよく似た復刻版を作ってしまったら、どうなるのでしょう。
八田氏:それは裁定制度そのものの話というより、出来上がったAさんの作品とBさんの作品が類似しているかどうか、依拠しているかどうか、という著作権侵害の一般的な問題です。その場合は、制度の利用にかかわらず必要に応じて当事者間で話し合っていただくことになります。
裁定制度が対象とする権利は財産権のみ
――もう一点、権利には財産的な側面(複製権など)と、著作者の人格的な側面(同一性保持権など)がありますよね。この制度でカバーされるのはどこまででしょうか。
八田氏:裁定制度が対象とするのは、財産権としての著作権です。著作者人格権は対象外です。
例えば、あるゲームのリメイク版を裁定制度のもとで制作したとして、その際の改変の内容や程度によっては、後から現れた原作者が「自分の意図に反する改変だ」と主張し、著作者人格権(同一性保持権)の侵害を訴える、という可能性は否定できません。
もしもそうした事態になったら、裁定制度では解決できず、当事者間で話し合っていただく、あるいは裁判を通じて結論を出すことになります。
もし後から「本物の権利者」が現れたら?
――裁定を受けて著作物を利用していたら、「私が本当の権利者です」という方が後に現れた場合、どうなりますか? 訴えられたりするのでしょうか。
八田氏:まず、裁定を受けた効果として、裁定を受けた範囲での利用は適法です。そのため、その利用行為を「著作権侵害だ」と訴えられても、適法な行為と主張できます。
ただし、権利者は、利用の対価として供託されている補償金を受け取る権利があります。この補償金の額は、通常のケースで支払われるであろう使用料の額に相当するものになるよう裁定の際に算定されるのですが、もしその補償金の額が通常の使用料の額に比べて低い、といった理由で不服がある場合は、利用者に対する訴訟で補償金の額を争うことになります。
また、その後の利用がどうなるかは、2つの制度で対応が異なります。
現行制度:権利者が現れても、裁定を受けた範囲での利用は継続できます。それ以上の利用(増刷など)が必要になった際については、以降は権利者と直接交渉していただくことになります。
新制度:権利者が現れた場合、利用者への通知など一定の手続を経た上で、裁定は取り消されます。裁定が取り消された後も利用を継続したい場合は、当事者間で、継続した利用の可否や条件について協議していただくことになります。
今回の取材からは、権利者不明の著作物を巡る課題に対し、文化庁が二つの制度をもって柔軟に対応しようとする姿勢がうかがえました。特に、これまで多くのケースで壁となっていた「返事がない」場合にも対応する新制度は、レトロゲームの復刻などを手掛ける開発者にとって、大きな一歩となるかもしれません。
また、現行制度についても、海外のゲームなどについての扱いが今回のインタビューで明らかになったことで復刻の範囲が広がった可能性もあるかもしれません。
もちろん、個々のケースではそもそも裁定が認可されるか否かといった部分もあるうえ、制度を利用すれば全てが解決するわけではありません。著作者人格権の問題や、海外での利用など、注意すべき点は多いです。
しかし、文化的資産であるゲームを未来へ適法な形で繋いでいくために、こうした制度の存在を知り、正しく理解しておくことは、ゲームを愛するすべての人にとって有意義なことだと言えるでしょう。
Game*Sparkでは、今後もゲームの文化的保存に関する動向に注目していきます。
(取材協力:文化庁)
未管理著作物裁定制度 | 文化庁